2025年の夏至はいつ?どんな意味があるの?この記事では夏至の基本知識から、開運習慣・食べ物・おすすめの過ごし方まで、今さら聞けない情報をわかりやすくご紹介します。
夏至とは?一年のうちで最も昼が長い日
夏至は、太陽の高さが最も高くなり、昼の時間が最長となる特別な一日です。実は昔から農業や行事とも深い関わりがあります。
2025年の夏至は6月21日(土)
国立天文台の暦によると、2025年の夏至は6月21日。毎年6月21日頃に訪れ、暦の上で「夏本番の入口」とも言われます。
2025年の夏至は、6月21日(土)です。
この日は、太陽が1年の中で最も高い位置を通り、昼の時間が最も長くなります。
わたしは毎年、夏至になると「あ、もうすぐ本格的な夏が始まるな」と感じます。
梅雨の合間でも晴れると、とても日差しが強くなる時期でもあります。
夏至は、太陽が北回帰線の真上を通過することで生まれる現象です。
このため、北半球の多くの地域では1年の中で昼が長く、夜が最も短くなります。
私の家では「今日は夜が短いから、ゆっくりする時間を意識的に取ろう」と意識して過ごしています。
一日の長さを感じられることが、なんだか特別に思えるんです。
カレンダーでは特に祝日ではありませんが、二十四節気のひとつとして季節の節目でもあります。
学校の理科の授業で覚えた人も多いと思いますが、大人になって改めて意味を知ると面白いですよ。
私もブログを書くようになってから、自然と暦に興味を持つようになりました。
「ただの日」じゃなく、「意識して過ごす日」になる感覚が好きです。
夏至のあとは少しずつ日が短くなっていきます。
ただし実際に「日が短くなった」と体感するのは8月下旬ごろが多いです。
わたしは毎年、夏至を境に「今ある時間を大切にしよう」と気持ちを新たにしています。
時間と太陽を意識することは、自分の生活リズムを整えるきっかけにもなります。
なぜ昼が長くなるの?天文的な意味とは
地球の傾きと太陽の位置が関係しており、北半球では太陽が最も高い角度を通るため、昼が長くなる現象です。
夏至に昼が長くなるのは、地球の「公転」と「地軸の傾き」が関係しています。
地軸は23.4度傾いているため、太陽が真上にくる位置が季節によって変わります。
この傾きにより、北半球では6月に太陽が最も高い角度を通り、昼が長くなるのです。
理科の授業で一度は習ったことが、改めて「実感」に変わる瞬間です。
夏至の日の東京では、日の出が4:25頃、日の入りが19:00頃と、14時間以上も太陽が出ています。
この長さは冬至(昼が最も短い日)と比べると約5時間もの差があり、自然の力を感じます。
私の家ではこの日、朝の光で目覚めて、ゆっくり朝食を楽しむのが恒例になっています。
日常に自然のリズムを取り入れるだけで、生活が少し豊かになります。
ちなみに、夏至を過ぎても「暑さのピーク」はまだ先に来ます。
これは“気温のタイムラグ”によるもので、地面や空気が本格的に熱を持つのは7月以降です。
わたしはこの豆知識を知ってから、「夏至って不思議だな」と興味がわきました。
自然や天体のことを知ると、毎日の空がもっと面白く見えてきます。
天文学的に見ると、夏至は「太陽の軌道が最も北に偏る」タイミングです。
夏至以降は太陽の位置が少しずつ南に下がっていき、日の長さが短くなっていきます。
この周期があるからこそ、春夏秋冬があるんですね。
人間の暮らしが宇宙のサイクルとつながっていると感じると、なんだかワクワクしてきます。
夏至にまつわる日本の風習や行事
日本では夏至に関連する特定の風習は少ないものの、地方によっては農業や漁業に関する儀式が行われています。
関西では「タコ」を食べる風習がある
大阪など関西地方では、夏至にタコを食べて豊作祈願をする習慣があり、「タコの足のように根が張る」ことに由来します。
関西では、夏至の日に「タコ」を食べるという風習が今も残っています。
その由来は、タコの足がしっかりと地面に張りついていることから「稲の根がよく張るように」という願いが込められているそうです。
わたしは大阪の友人からこの話を聞いて驚き、夏至にあわせてたこ焼きを作ってみたことがあります。
地域ならではの習慣って面白いですよね。
特に農業が盛んな地域では、作物の生育を祈る日としても意識されているそうです。
農村部では「田植えの後に栄養のあるものを食べる」という意味合いもあるとのこと。
わたしの家では、それ以来夏至には意識して魚介類を取り入れるようになりました。
季節と食べ物をつなげると、毎日の食事も少し楽しくなります。
タコの他にも、関西では「夏野菜をたくさん食べる」「梅干しを仕込む」といった家庭内の行事が行われていることもあります。
古くからの風習が家庭ごとに残っているのも、日本文化の魅力のひとつです。
私の知人の家庭では、夏至の日に手作りの酢だこを食べるのが恒例だそうです。
こうした話を聞くと、自分の家でも新しい習慣を作りたくなりますね。
特別な祭りや大きな行事は少ないものの、こうした風習を知っておくと、季節の変わり目を意識するきっかけになります。
「今日ってただの木曜じゃなかったんだ」と気づくことで、日常が少し彩られます。
わたしはその感覚を味わうために、ブログでこうした季節行事を調べて発信するようになりました。
情報としてだけでなく、気持ちの切り替えにもなるのが夏至のような節目です。
全国の神社で「夏越の祓」も近い
夏至の少し後に行われる「夏越の祓(なごしのはらえ)」も関連行事のひとつ。半年の穢れを祓う神事です。
夏至の1週間後〜月末にかけて、全国の神社で「夏越の祓(なごしのはらえ)」という神事が行われます。
これは6月の締めくくりとして、半年分の“罪・穢れ”を祓い、心身をリセットする行事です。
私も毎年、地元の神社に参拝して「茅の輪(ちのわ)」をくぐる儀式に参加しています。
心が軽くなる感覚がとても気持ちよく、毎年の恒例行事になりました。
この「茅の輪」は、神社の境内に大きな草の輪として設置され、それを「8の字」にくぐることで厄を祓うとされます。
ルールはありますが、難しくないので初めてでも安心して参加できます。
わたしの家族も去年は一緒に行き、「これで夏が始まる感じがするね」と話していました。
神社によっては短冊を書いたり、人形(ひとがた)に名前を書いて流す儀式もあります。
本格的な夏が始まる前に、身体と心を整える意味合いで、多くの人が参拝しています。
私自身も、上半期にたまった疲れや悩みを“神様に預ける”気持ちで参加しています。
そうすると、後半もがんばれそうな気がしてくるんですよね。
夏至の時期と重なることで、自然と自分の内側に向き合えるタイミングにもなります。
神社では夏越の祓の限定お守りや、茅の輪くぐりの特別札なども頒布されています。
ご利益や意味を知ったうえで持ち歩くと、旅先のお守りにもなりますよ。
わたしは毎年、お守りを手帳に入れて持ち歩きます。
夏至から始まる“後半の運気アップ”を願う小さな習慣です。
夏至の日に食べるとよいとされる食べ物
夏至に特別な食事をする文化も一部に残っています。季節の変わり目にふさわしい、体を整える料理をご紹介。
旬の野菜を使った「夏越ごはん」
雑穀ご飯に夏野菜をたっぷり乗せた「夏越ごはん」は、2020年から広まりつつある新しい風習。栄養満点です。
「夏越ごはん」は、雑穀米の上に夏野菜の天ぷらや和え物をのせて食べるスタイルの行事食です。
栄養バランスがよく、見た目も華やかで、2020年ごろからSNSを中心に広まり始めました。
私も昨年、初めて家で作ってみましたが、彩りが良くてテンションが上がりました。
食卓に季節感があるだけで、気持ちも前向きになります。
使う野菜は、なす、ピーマン、かぼちゃ、オクラなどがおすすめです。
揚げ物にしてもよし、煮びたしやおひたしでさっぱり仕上げてもOK。
私はかぼちゃとズッキーニの天ぷらをのせてみましたが、子どもにも好評でした。
旬の野菜は栄養価も高く、身体を内側から整えてくれます。
「雑穀ごはん」は、白米にキヌアやもち麦などを混ぜるだけでOKです。
わたしの家では、もち麦を入れるとぷちぷちした食感が楽しいと人気です。
雑穀は食物繊維が豊富で、夏の疲れた胃腸にも優しいんですよ。
こうした小さな健康意識を、行事に重ねて取り入れるのがとても自然です。
「季節を食べる」というのは、昔から続く知恵でもあります。
特に夏至は、体力や免疫力が落ちやすい時期の節目なので、しっかり食べて整えることが大切です。
わたしは毎年、夏越ごはんを通して「よし、後半戦もがんばろう」と自分に声をかけています。
美味しくて体にも良い、そんな行事食を取り入れてみてはいかがでしょうか?
さっぱり冷たい料理で体をクールダウン
梅干しやそうめん、冷やし中華など、暑さで食欲が落ちる時期にはぴったり。食事で夏バテを予防しましょう。
夏至の時期は、湿気と暑さで食欲が落ちやすくなります。
そんなときは、冷たくてさっぱりした料理が身体にも心にも嬉しい存在です。
私のおすすめは、梅干しと薬味たっぷりの冷やしそうめん。
ツルっと喉ごしがよく、忙しい日の昼食にもぴったりなんです。
梅干しにはクエン酸が含まれていて、疲労回復効果が期待できます。
わたしは夏バテ気味のとき、梅干しと大葉を刻んだ“梅しそそうめん”をよく作ります。
冷房の中で体がだるくなることも多いですが、こうした料理で元気を取り戻せます。
ちょっとした薬味が、味のアクセントにもなりますよ。
冷やし中華や冷製パスタも、夏の定番料理です。
酢を効かせたり、レモンを添えると、さらに爽やかな味わいになります。
我が家では週末の昼に「冷たい麺の日」を作って、家族で夏メニューを楽しんでいます。
食べることが楽しみになるだけで、暑さも少し乗り越えられます。
冷たいデザートもおすすめです。特に、みぞれ寒天やフルーツ入りのゼリーなどは、夏至にぴったりの涼感スイーツ。
私は地元の桃を使ったゼリーを手作りしてみたら、意外と簡単で美味しくて驚きました。
季節の果物を使えば、自然の甘みで満足度も高まります。
この時期だけの“食”を楽しんで、元気に夏を迎えましょう。
夏至と開運の関係|スピリチュアル的な意味
実は夏至は、エネルギーが最高潮になる日とも言われ、浄化や運気の転換期とされるスピリチュアルな日でもあります。
太陽のパワーを受け取る日として注目
一年で最も太陽が長く出ているこの日は「太陽の気」を取り入れるのに最適。朝日を浴びるだけでも運気アップの効果が。
夏至は、太陽のエネルギーが一年で最も強くなる日とされ、古代から「太陽の祝福を受ける日」と考えられてきました。
特にスピリチュアルの世界では、浄化やスタートに適した“高波動の日”と位置づけられています。
わたしは毎年この日、朝一番にカーテンを開けて太陽の光をしっかり浴びるようにしています。
それだけで不思議と元気が湧いてくるから不思議です。
夏至の日は「心の切り替え」にも最適な日です。
光が強くなるということは、心の中にたまった暗いエネルギーを手放しやすいタイミングでもあります。
私の家では、朝日を浴びながら1分だけでも目を閉じて「ありがとう」とつぶやく小さな習慣があります。
その習慣があるだけで、1日を穏やかに始められるようになりました。
ヨガや瞑想、呼吸法もこの日に行うと、普段より深く集中できると言われています。
私も夏至には特別に朝ヨガを取り入れていて、太陽礼拝という動きを丁寧に行っています。
太陽のエネルギーを身体全体で受け取っている感覚がとても心地よいんです。
身体がぽかぽかと温まり、気分も晴れやかになります。
「太陽の光」は自然のヒーリング力とも言える存在です。
夏至はそれを意識的に受け取れる特別なタイミング。
特に2025年は土曜日と重なるため、ゆっくり朝日を浴びる習慣を始めるにはぴったりの日です。
今年からはじめてみるのもおすすめですよ。
断捨離や掃除でエネルギーのリセット
不要な物を捨てたり、部屋を整えたりすることで、夏至のパワーを味方に。心もスッキリ軽やかに整います。
夏至は「気の転換点」とも呼ばれる日で、物理的・精神的な整理にぴったりなタイミングです。
特に、身の回りの整理整頓や断捨離は運気をリセットする第一歩になります。
わたしは夏至の日の朝に、靴箱や冷蔵庫など見落としがちな場所をあえて掃除しています。
目に見える空間が整うと、心の中もスッキリしてくるから不思議です。
スピリチュアル的にも「空間を空けると新しいエネルギーが入る」と言われています。
古いものや使っていないものを手放すことで、自然と新しい流れが入りやすくなるのです。
私の家では、使っていない服を整理したあと、気持ちの切り替えがスッとできた経験があります。
物と心はつながっていると実感しますね。
断捨離にあわせて「お香」や「アロマ」で空間を浄化するのもおすすめです。
夏至に合わせてラベンダーやレモンの香りを焚くと、すっきりとした気持ちで新しい季節を迎えられます。
わたしはお気に入りのハーブスプレーを部屋中にシュッとひと吹き。
その瞬間、空気がリセットされたような心地よさを感じます。
また、デジタル断捨離=スマホの写真整理やフォルダの掃除も有効です。
わたしは毎年夏至の前後で、写真フォルダを見直し「いまの自分に必要なもの」を意識的に選び直します。
心の整理と同じように、情報の整理もこの時期にすると後半の時間が有効に使えます。
夏至のエネルギーを活かすコツは「手放すこと」なのかもしれません。
夏至におすすめの過ごし方5選
ただ「昼が長い日」で終わらせるのはもったいない!夏至をもっと有意義に過ごすためのアイデアをご紹介。
朝の時間を活用してパワーチャージ
早起きして朝散歩やヨガなどを行えば、太陽の恩恵を全身で感じられます。朝活にはぴったりの日です。
夏至は、朝日が最も早く昇る日でもあります。
だからこそ、早起きして「朝活」を始めるには絶好のチャンスです。
わたしは夏至の朝、5時台から外に出て軽く散歩をするのが恒例になっています。
人も少なく、空気が澄んでいて、思わず深呼吸したくなる時間です。
朝の時間帯は、脳が最もクリアな状態にあると言われています。
静かな環境で読書や日記を書いたり、ゆっくりコーヒーを淹れてみるのもおすすめです。
私の家ではこの日に限って、家族それぞれが「好きなことだけする朝」と決めています。
ちょっとした自由時間が、1日をすごく充実したものにしてくれるんです。
ヨガやストレッチなど、体を動かす習慣をスタートするのにもぴったり。
夏至の朝に太陽礼拝を行うと、太陽のエネルギーをまっすぐ体に取り入れられる気がします。
私は15分だけでもヨガマットに座って、深呼吸する時間を大切にしています。
それだけで一日のリズムが整うので、夏の朝のルーティンにおすすめです。
朝から良いスタートが切れると、自然とポジティブな気分で1日を過ごせます。
たとえ特別なことをしなくても、夏至の朝に“自分のための時間”を持つだけで気持ちが変わります。
この小さな習慣が、夏の始まりに大きな意味を持つように思えます。
ぜひ今年の夏至は、ちょっと早起きして朝時間を楽しんでみてください。
キャンドルナイトで電気を消す夜
夏至の日には「100万人のキャンドルナイト」というイベントも。夜は電気を消して、静かな時間を楽しんでみては?
夏至の夜に電気を消してキャンドルを灯す「100万人のキャンドルナイト」は、全国で広がるムーブメントです。
2003年に始まり、「でんきを消して、スローな夜を。」というコンセプトのもと、毎年多くの人が参加しています。
わたしも数年前からこのイベントに参加するようになり、照明をすべて消して、キャンドルの灯りで夜を過ごしています。
最初は不便に感じたものの、今ではこの時間がとても心地よく感じるようになりました。
キャンドルのやさしい光に包まれるだけで、心が穏やかになります。
テレビやスマホをオフにして、家族と静かに話したり、本を読んだりするだけでも特別な時間です。
私の家では、夏至の夜にアロマキャンドルを焚いてリラックス時間を過ごしています。
この“非日常”な空気が、心にとても良い影響を与えてくれると感じています。
小さなグラスキャンドルやLEDキャンドルでも雰囲気は十分楽しめます。
安全面が気になる方は、火を使わないタイプを選ぶと安心です。
子どもがいる家庭では、手作りキャンドルや紙ランタンを作って楽しむのもおすすめです。
我が家も今年は子どもとキャンドルホルダー作りにチャレンジする予定です。
夏至の日に電気を消すという行為は、自然との距離を縮める体験でもあります。
便利さから少し離れることで、本来の自分に戻れるような感覚があります。
わたしはこの夜を「気持ちをリセットする時間」として大切にしています。
ぜひ今年は、あなただけの“スローな夏至の夜”を過ごしてみてください。
2025年の夏至はいつ?意味・風習・過ごし方まとめ
2025年の夏至は6月21日(土)。一年で最も昼が長くなるこの日は、自然のリズムに耳を傾け、自分を整えるチャンスの日。意味を知って過ごすだけで、いつもと違う1日になるはずです。
2025年の夏至は6月21日(土)です。
この日は昼が最も長く、太陽のエネルギーが最高潮に達する特別な一日。
ただの日常として過ごすのではなく、自然や季節の流れを意識することで、心と体のリズムを整える大きなきっかけになります。
私もこの日を境に、生活のペースを見直したり、意識的に深呼吸する時間をつくったりしています。
タコを食べる関西の風習や、全国の神社で行われる「夏越の祓」など、地域に根付いた伝統も面白いポイント。
日本人として知っておきたい文化や行事が、夏至にはさりげなく詰まっています。
わたしはこうした季節の知識をきっかけに、子どもと一緒に暦や星の話をするようになりました。
家族の会話にも深みが増すのが嬉しいです。
また、夏至はスピリチュアル的にも「浄化・再スタート」の日とされ、自分を見つめ直すには最高のタイミング。
断捨離、早起き、キャンドルナイトなど、小さな行動を通して心の整理ができます。
私の家では、この日に合わせて写真フォルダを整理したり、ベランダの植物を植え替えたりするのが恒例です。
日々の暮らしの中に小さな区切りを入れることで、気持ちにメリハリが生まれます。
2025年の夏至は週末にあたるので、例年以上に「特別な1日」として過ごしやすいはずです。
ぜひ太陽の光を意識して浴びたり、季節の料理を味わったりして、自分らしい過ごし方を楽しんでください。
自然とともにある感覚を取り戻すことで、心も体も軽やかになりますよ。
今年の夏至が、あなたにとって気持ちのいい節目になりますように。

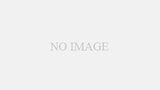
コメント